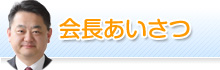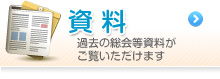地域とともに育てる~「茶の心」を育てる「茶育」の取組~
西尾市立西野町小学校
1 はじめに
本校のある西野町地区は、西尾市の北部、矢作川に面した茶畑の広がる地域にある。西尾市は、日本有数の抹茶の産地であり、その多くを担うのが、本校区、西野町である。学校では、「おまっちゃくん」 というキャラクターが行事に登場するなど、子どもたちには「抹茶の西野町」があたりまえになっている。そのあたりまえの背景にある「こと」、そこに関わる「人」を見つめ、体験し、真に分かることで、「思いやりの心」「ほっとする心」「ふるさとを思う心」という「茶の心」を育てる「茶育」を実践している。
2 「茶の心」を育てる「茶育」の取組

校内茶摘みの様子
3年生になると、地域の茶業クラブの協力で、昔ながらの製法「手もみ茶」を体験させていただく。これをきっかけに、地域の茶農家の見学や聞き取りに出かけ、総合的な学習や社会科を進めていく。
茶業クラブや茶農家の方と繰り返し関わることで、「ふるさとを思う心」が醸成される。
本校は運動場に「御所ノ下茶園」と呼ばれる茶畑がある。茶業クラブの方が管理してくださり、毎年5月になると、ここで4年生が初めての茶摘みを行う。伝統である手摘みによる収穫は、新芽だけを丁寧に摘むことで、抹茶の質を落さないことにつながっている。この体験でも西野町の茶を大切にしようとする「ふるさとを思う心」が育つ。4年生が摘み終わった後、5、6年生が摘み残しはないか確認しながら仕上げを行うことで、上学年として「思いやりの心」が育まれていく。
この「校内茶摘み」を終えると、茶農家の茶畑へ「校外茶摘み」に出かける。農家の方に摘ませていただいている、人が飲むものを摘んでいるという思いをもち、茶摘みを行う。学年を経るにしたがい、摘み方が上手になり、摘み量も増えていくとともに、「思いやりの心」「ふるさとを思う心」も高まっていく。

西野町茶会の様子
「校外茶摘み」で摘んだ茶葉は、抹茶となり、子どもたちの手元に届く。6月には、本校体育館で「西野町茶会」が行われる。この茶会では、5、6年生が1~4年生と地域の方、保護者をおもてなしする。1~4年生は、保護者と一緒に座り、おもてなしを受けることで「ほっとする心」「ふるさとを思う心」で満たされる。加えて4年生は、5、6年生の凛とした姿にあこがれ、自分たちももてなす側になりたいとの思いを高めていく。この5、6年生の姿は、お世話になっている方々への感謝の気持ち「思いやりの心」
の現れである。この気持ちを姿で現すため、5、6年生は、本校茶道部講師の指導を受けながら「5、6年茶会」を開き、作法を学んでいる。
コロナ禍で地域の方を招待できない年が続いたが、昨年度より「思いやりの心」「ふるさとを思う心」を育てる機会を逸しないよう方法を工夫し、以前と同じ招待する形に戻した。
3 おわりに
茶業に関わる方々だけでなく、米作り農家、校区の歴史を語ってくださる方々など、西野町は、地域の教育力の高い校区である。働き方改革が言われる中、さまざまな課題はあるものの、これからも地域とともに西野町っ子の「心」を育てていきたい。